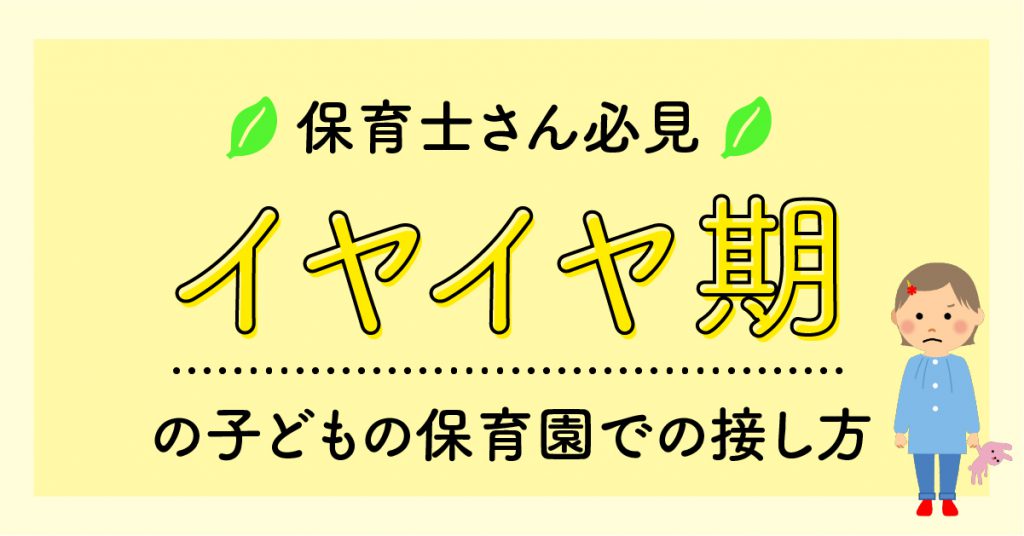

上記リンクよりご覧ください!
保育園で働く保育士さんが出会う機会が多いのが、子どものイヤイヤ期です。
イヤイヤ期の子どもに手を焼くのは保護者だけでなく、保育士さんも同じです。
子どものイヤイヤ期が原因で、いつも通りに仕事ができなかったり、うまく接することができず落ち込んでしまったりという保育士さんもいます。
保育対象の子どもがイヤイヤ期になったときにはどのように接するべきなのか、対応方法を知っておきましょう
保育士さんが知っておきたい!子どもたちのイヤイヤ期
言うことを聞いてくれない、何を言っても泣いてしまう、そんな状態の子どもたちの対応に困ってしまう保育士さんがたくさんいます。
「いつもならこんなはずじゃないのに…」というときには、お家でなにか変わったことがないか、子どもの体調は大丈夫かなどと合わせてイヤイヤ期の可能性も考えてみましょう。
イヤイヤ期ってどんなの?
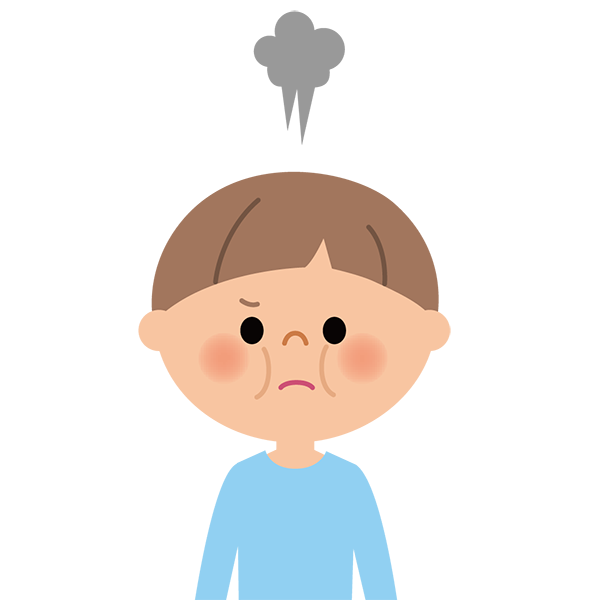
イヤイヤ期は子どもが言うことを聞いてくれなかったり、何に対しても嫌!と言ったり、不満があるととにかく泣くという時期や期間のことです。
普段ならお利口なはずなのに、何に対しても泣いたり反抗したりを繰り返す子が多く、子育ての方法に悩む保護者も多いです。
イヤイヤ期の子どもはお家の中だけでなく、保育園でも同様の状態になることが多く、子どもとの向き合い方に困る保育士さんも多いようです。
イヤイヤ期は自己主張のはじまり

子どもがイヤイヤ期になる時期や年齢には差がありますが、おおむね1歳〜2歳頃であることが多いです。
イヤイヤ期は子どもの中に「自己」や「自我」が芽生えることによって起こるとされていて、成長の証でもあります。
まだまだ保護者がいないと生活することが難しい年齢ですが、あれがしたい、これはいや、と自分で選択することが自立をすることの第一歩と言えます。
また、周りの大人に甘えたいという気持ちや、疲れた・眠い・しんどいといった気持ちをうまく表現できない、ということがイヤイヤにつながることもあります。
イヤイヤ期は誰もが通る道であり、子どもの成長過程で起こるものとして受け入れていく必要があります。
イヤイヤ期は子どもならみんななる?

必ずしもみんながイヤイヤ期を経験するとは限りません。
二人以上のお子さんがいる保護者の中にも、お兄ちゃんは大丈夫だったけど妹はイヤイヤ期があった、という人もいれば、二人ともイヤイヤ期があったという人もいます。
一方でイヤイヤ期がなかったという場合もあります。
同じ月齢の子が集まる保育園でも、イヤイヤ期がある子とない子がいるため、全員に同じ対応をすれば良いというわけではないことを覚えておきましょう。
誰しもが通る道ではないからこそ、保護者も悩んでしまうため、保育園や保育士のサポートが必要です。
保育園でのイヤイヤ期ってどんなの?
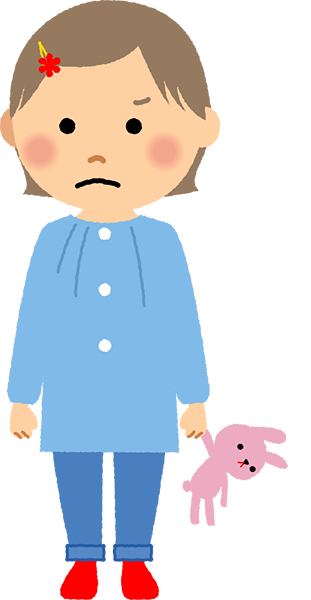
保育園で起こるイヤイヤ期の具体例として次のようなものがあります。
- 朝登園したけど教室に入ってくれない
- 昼食の時間になっても遊びを続けてご飯を食べてくれない
- 水やご飯をこぼす
- できないことも一人で全部やろうとする
- できることを手伝ってもらおうとする
一見子どもなら誰もがやりそうとも思えることですが、何に対しても反抗されて一日のスケジュールが予定通り進まないことや、他の子を見られない状態になることもあります。
ですが、イヤイヤ期の子どもを突き放すようなことはNGです。
ひとりひとりと向き合ってその子に合った方法で接することが大切です。
保育士さん必見!保育園で起こるイヤイヤ期の対処法!
ここからは、実際に保育園で働く保育士さんに実践して欲しいイヤイヤ期の対処法をご紹介します。
預かる子どもがイヤイヤ期だったときには、その子に合った接し方を探して、子どもを尊重する方法で接するようにしましょう。
否定しない
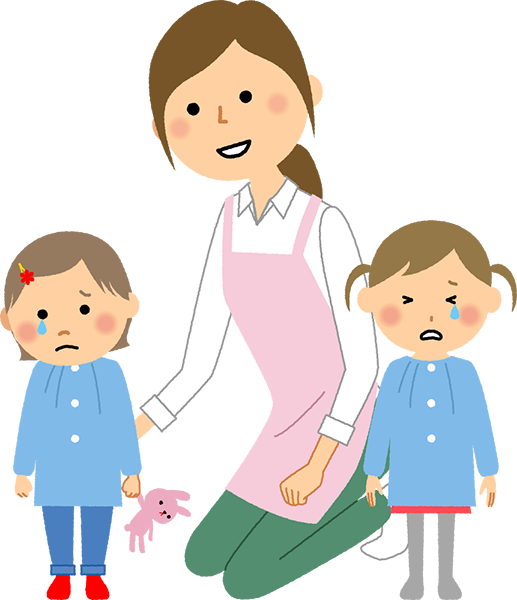
イヤイヤ期の子どもは、それじゃなくてあれがいい、あっちに行きたい、など自分のやりたいことをぶつけてくることが多いです。
それに対してなんでも「ダメ!」と否定してしまうのは避けましょう。
まずは子どもの気持ちを受け入れてあげる、そしてやりたいことはやらせてみて、サポートしながら見守ってあげましょう。
ただし、危険な行為に対しては優しくダメなことを伝えて、理由を説明してあげるようにしましょう。
イヤイヤ期の中で、やって良いこととダメなことをしっかり学ぶ機会を作ってあげることが大切です。
脅しや交換条件はNG

「〇〇しないとオバケが出るよ」「〇〇ができたらお菓子をあげるよ」などの交換条件を出してイヤイヤ期をクリアしようとするのも避けましょう。
子どもを脅して恐怖で支配することで、何がいけないのかわからないままになってしまいます。
また、保育園で交換条件を出すことでお家でも同じことができると思い込んでしまう子どももいます。
保育園で余計なことを覚えさせられた、と感じてしまう保護者もいるため、子どもに交換条件を出すのはやめましょう。
他のもので気持ちを切り替える
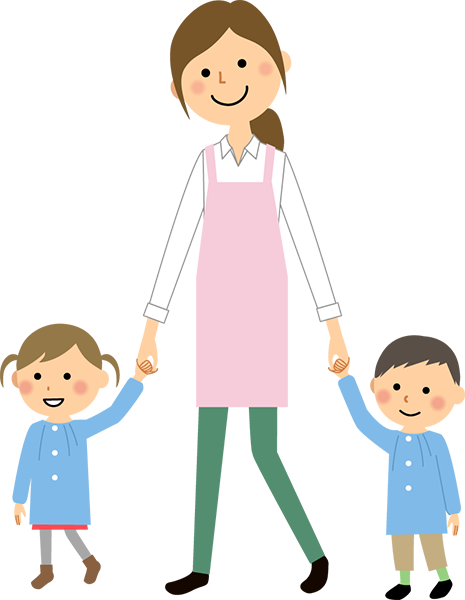
イヤイヤ期の子どもには、気持ちを切り替える機会を与えてあげることも大切です。
一つのことに嫌!という気持ちや不満が向いている状態から、他のものに気が向くような対応をしてみましょう。
他の方法を提案してみる、他のものに興味を逸らしてみることで、子どもの気持ちがリセットされることもあります。
「こんなのはどう?」「これやってみない?」と子どもに投げかけてみましょう。
保育園のイヤイヤ期は成長のチャンス
今回ご紹介した対処法はほんの一例にしかすぎません。
イヤイヤ期の子どもと向き合うことで、その子に合った接し方を見つけてあげることが大切です。
また、イヤイヤ期は子どもが成長するチャンスでもあります。
保育士さん成長をサポートできるよう、子たちはもちろん保護者のケアも忘れずに行いましょう。



